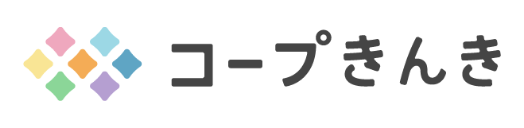- ホーム/
- 商品のこと/
- つくるひと つくるところ/
Productつくるひと つくるところ
「人」がわかると商品もわかる。コープの商品に携わる“中の人”をとおして想いを届けます。

From鳥取県株式会社井ゲタ竹内のお仕事流儀
沖縄の美しい海から組合員の食卓へ
「心の味」を追求する
もずくのエキスパート
2025.08.22
株式会社井ゲタ竹内
「CO・OP恩納村産味付糸もずく」
「CO・OP沖縄県産味付太もずく」
※お取り扱いは生協によって異なります。
INDEX
口に運んだ瞬間、口内に広がる爽やかな酸味とツルリとのどごしの良いぬめり、そしてほんのり漂う磯の香りが相まって、独特の味わいを楽しませてくれるもずく。
特徴的なぬめり成分は、フコイダンという水溶性食物繊維の一種で、低カロリーということもあり食卓の人気者です。
そんなもずくの魅力をいち早く全国に広め、さまざまな味付けを展開しファンを増やし続けているのが、鳥取県境港市に本社を構える株式会社井ゲタ竹内(以下、井ゲタ竹内)。コープでは「CO・OP恩納村産味付糸もずく」や「CO・OP沖縄県産味付太もずく」が、人気のロングセラー商品です。
全国に広がり定番商品となった理由を、井ゲタ竹内に足を運び教えていただきました。
INTERVIEW

社長である竹内隆一郎さんを中心にした井ゲタ竹内のみなさん。
「家庭で作られる料理のように、食べてもらう人の姿を想像し、心を込めた商品作りを心がけています」
戦後いち早く添加物を
極力使わない商品を届けたいと奮闘
日本海に面した港町で、全国でも有数の漁港を持つ鳥取県境港市。豊富な海の幸が水揚げされるこの地で、井ゲタ竹内の創業者・竹内孝氏が事業を始めたのは、1947年(昭和22年)のことでした。
「竹内孝は太平洋戦争で本当に辛い思いをし、生き永らえることができた意味、意義、使命を問い続け、生涯を命の恩返しに捧げようと決意しました。その経験から『人の役に立ちたい』、そして自分たちが作る商品は小手先のものであってはならず『すべて本物でなければならない』と言う強い信念のもと、心を込めた自然な手作りの味に行きつきました」。そう教えてくれたのは、今回お話をお聞きした常務取締役の竹内 周さんです。
はじめは境港で佃煮製造に着手しましたが、当時から添加物を極力使わず安全で体に良いものを作るという、他社とは一線を画す独自の哲学を掲げていたという井ゲタ竹内。
「添加物を使わないしょうゆ、と言ってもなかなか作ってもらえない。当時私は小さい子どもでしたが、原料素材が手に入りにくい時代でしたから随分苦労している父の姿はよく覚えています」。
やっと特別に作ってくれる会社がみつかり商品化にこぎつけた後も、「添加物を使っていない」という価値はなかなか理解されなかったそうですが、その後時代が変わって社会的な共感を呼ぶことになります。

井ゲタ竹内常務取締役の竹内 周さん。
「体にさわらず(悪い影響がなく)、少しでも健康になるものを」と社員全員が使命に燃えて携わっています」
「安全な商品作り」という共通の
価値観のもと
井ゲタ竹内と生協は
信頼関係を築き上げてきました
「昭和40年代に入ると、公害問題などから世の中の安全な食材への関心がグッと高まりました。そこで井ゲタ竹内の『添加物を使わない』という考え方が社会に受け入れられ始めたんです。
そして1971年(昭和46年)にはもずくを初めて商品化しました。
当時は隠岐島のもずくを販売していました。山陰地方の郷土食なので全国的には知られていませんでしたが、化学調味料無添加の味付けをして販売し、生協とのお取り引きが始まって、共同購入などで広く認知されるようになりました。
量販店で店頭に並び始めるのは1990年代以降なので、もずく市場を開拓し、その火付け役となったのは、生協といっても過言ではありません」。
漁協との信頼関係を大切に築き
海を汚さない、
沖縄県産のもずくが誕生

恩納村漁協組合長の金城治樹さん。
収穫したばかりのもずくを手ににっこり
昭和50年代には「味付もずく」が全国に広がりましたが、隠岐島では「磯焼け」と呼ばれる海藻の生育環境が悪化する現象が進行し、収穫量は年々厳しいものになりました。この危機に直面して、井ゲタ竹内は新たな生産地として沖縄県に着目しました。
沖縄でもずくの養殖が試験的に始まり、安定的な生産が見込まれるようにはなりましたが、当時の沖縄と「本土」との間には、歴史的な距離感がありました。沖縄県の地元銀行や漁協との信頼関係を築くのが大変だったと竹内さんは語ります。
「誠実な姿勢で漁協との関係を築いていくしかありませんでしたね。技術支援を通じて品質基準の明確化や確実な買い取りの保証をすることで、生産者の自立を支援してきました。特に恩納村漁協組合とは深い関係を築いています。恩納村漁協が「海を汚さない漁業」として海藻養殖に特化していることも、井ゲタ竹内の理念と合致していました」。
-

海中でのもずく収穫の様子。
吸引機でやさしくもずくを収穫します -

収穫したもずくは船上へ。
おいしいもずくを届けるため
1977年(昭和52年)、恩納村漁協が全国に先駆けてもずくの養殖に成功すると、苗床技法を開発し、もずくが沖縄の一大産業となる礎を築きました。
「もずくの養殖は、まず種を保存して培養し、網に種を付けて浅瀬で芽出し(中間育成)をしたら、苗を海の深いところへ移動して本張りし、収穫まで育成します。収穫は太もずくが大体3月~6月、糸もずくが大体1月~3月です。収穫後は、塩漬けにして一斗缶に詰められて井ゲタ竹内本社工場へ届きます。
この時、品質管理のために生産者や収穫海域をさかのぼれるように記録して、一斗缶にも印字してトレーサビリティを確保しています。これも『安心安全なものを届けたい』という思いからです。
生産者と一緒に、原料の質を高めていくということが大事だと思っています」。

ロットナンバーを調べると、生産者や時期、収穫海域がわかります。
もずく原料が本社に届いてから商品になり出荷されるまでの流れは、次の通りです。
①検品(品質を確認し、5段階のグレードに分類)
②洗浄・選別(異物を除去)
③加熱・塩抜き(加熱殺菌し塩を抜く)
④自社配合の調味液を調合(調味液を自動で調合)
⑤充填・包装(カップにもずくと調味液を充填)
⑥検品(金属検出器・X線検査・重量チェック)
⑦検査(微生物検査・品質検査)
⑧出荷(商品をお届け)
もずくは細かい海藻なので貝やエビなどの海中生物が異物として混入してしまう可能性はありますが、選別工程で人の目と手の感触で取り除いています、と竹内さん。
「例えば網の繊維が混ざっていると、しっかりと目を凝らして手でもずくを触らないと見つけられません。とても集中力がいる作業なので1時間毎に休憩をとります」。


選別室は照明が近くなるよう天井が低くなっています。
選別しやすい明るさに調整された照明の下で、もずくを少量ずつ手で広げて異物を探します。
「絶対に異物混入させない」という気迫が漂っていました
選別を終えたもずくは、加熱・塩抜きされます。その後、カップにもずくと調味液が充填されます。
「全国のいろいろな生協様の味付もずくを製造させていただいています。その製品それぞれに地域であったり嗜好性によって味や規格が変わります。ただし全商品共通して、保存料や不要な調味料を使わない製品づくりを基本としています」。

カップに充填されるもずくと調味液。
カップごとに4桁のロットナンバーが印字されます。
井ゲタ竹内は、沖縄恩納村の「里海づくり」を支援しています。サンゴ養殖活動もそのひとつです。皆様からのご支援がこの活動に役立っています。
心を込めた仕事がお客様へ伝わると
信じています
「井ゲタ竹内が創業以来大切にしてきた『心の味』。それは儲けるためではなく、誰かに喜んでもらう、誰かの役に立つという創業者の思いに根差しています。心を込めた仕事が、お客様に伝わると信じて取り組んでいます。
また組合員さんには、里海づくりの取り組みを通して、一人ひとりの想いが集まると、1つの大きな形になるということを組合員さんから教えてもらいました。ありがとうございます。
これからも日常の中で私たちのもずくをおいしく楽しんでいただけることを願っています」。
※商品情報・役職等は取材当時のものとなります。
編集後記
みなさん穏やかな笑顔が印象的だった井ゲタ竹内さん。「心を込める」という気持ちが、お話ししていても伝わり、こちらも自然に笑顔に。そして歓迎の印にといただいたもずくの妖精の可愛い缶バッヂに、さらに暖かい気持ちになりました。ところで社名である「井ゲタ竹内」の「井ゲタ」って?と思った人も少なくないはず。
これには、井戸の枠である「井桁(げた)」のように一致団結し、力を合わせて会社を盛り上げ、世の中に役立つ仕事をしていく」という創業者の熱い思いが込められています。みなさんのこだわりと思いが、もずくのおいしさを全国へ広め、さまざまな「業界初」を打ち立てられたのだと感じました。